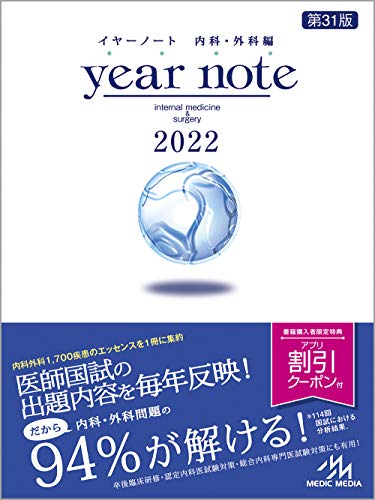内科学会セルフトレーニング問題の復習。
はじめに
2020年の内科学会セルフトレーニング問題の復習をしたいと思います。
主に自分が間違えた疾患、ポイントを箇条書きにします。
復習
・Advance care planning〈ACP〉の概要について。
・Meigs症候群。
・妊娠中の血糖値管理目標:
早朝空腹時 95 mg/dL未満,食後1時間値 140 mg/dL未満
もしくは食事2時間値 120 mg/dL未満
・内部被ばく:
セシウム → プルシアン・ブルーを用いる。
・低リスク群MDSの治療法。
・分枝型IPMNの悪性化は10年で約8%。
・多発血管炎性肉芽腫症。
・遺伝性出血性末梢血管拡張症〈Osler 病〉。
・ナットクラッカー(クルミ割り)症候群。
貧血も鉄欠乏もなければ経過観察。
・SIADH〈syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone〉。
希釈性の低Na血症。
・SLEの分類に必須な項目:抗核抗体80倍以上。
・気管支拡張症の急性増悪。
・G6PD異常症。
・がん遺伝子パネル検査。
・特発性正常圧水頭症。
・胃全摘術後の患者では,ビタミンB12欠乏と鉄欠乏が同時に存在しうる。
・巨赤芽球性貧血に鉄欠乏性貧血が合併→骨髄に後骨髄球。
・可逆性後頭葉白質脳症。
・トキシックショック症候群〈TSS〉。
おわりに
平均正答率を下回ってしまったので、ちゃんと復習していきたいです。
内科の範囲は幅広く、すぐに頭から抜けてしまうので定期的に勉強したいと思います。
【2019-2020版】日本内科学会 認定内科医試験 受験記 【試験対策】
■ はじめに

2019年7月7日、認定内科医試験を受験しました。
これまで「剖検」を取ることができない病院に勤務していたため、同期と比べてかなり遅くなりましたが、今年ようやく受験することができました。
認定内科医試験は2020年で最後となりますが、私が使った教材等について書きたいと思います。
来年度の受験生のために、少しでも参考になれば幸いです。
■ 目次
- ■ はじめに
- ■ 目次
- ■ 認定内科医試験とは?
- ■ 認定内科医試験の試験内容
- ■ 2019年に出題された主な内容(印象に残ったもの)
- ■ 私が使用した教材
- ■ Q-Assist
- ■ 試験の手ごたえ
- ■ そのほか
- ■ 試験の結果(2019年9月15日:追記)
■ 認定内科医試験とは?
一定レベル以上の実力を持ち、信頼される内科医を「認定内科医」として、さらに高い水準の内科診療能力を備えた認定内科医を「総合内科専門医」として認定する。
※日本内科学会HP(https://www.naika.or.jp/nintei/seido/tebiki/tebiki01/#1)より引用
上のような目的がありますが、現行の制度では各専門医試験を受験するうえで取得しておく必要があり、登竜門のような試験です。
■ 認定内科医試験の試験内容
・問題形式はマルチプルチョイス方式
(日本内科学会HPのQ&Aに詳しく書いてあります)。
・問題数は全300問。
・試験時間は100問 120分×3回。途中60分・40分の休憩があります。
・試験内容は全体的に国家試験に+αした程度の問題。
→ 自分の専門分野であれば余裕で解ける(……はず)
・内科全分野からまんべんなく出題される。
→ ヤマを張ることはあまり効果的でない。
・疾患名そのものを問う問題は少ない。
・疾患に特徴的な症候や検査を問う問題が多い。
・一方で、非常に初歩的な問題もポツポツみられる。
→ こういった問題を落とさないようにしたい。
■ 2019年に出題された主な内容(印象に残ったもの)
・ALSの治療薬 → リルゾール
・皮膚筋炎の抗体 → 抗MDA5抗体
・多発性硬化症 → オリゴクローナルバンド
・アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 → CTで高吸収粘液栓
・ウイルス性肝炎(A・B・C・E型)すべて
・IgG4関連疾患
・クリプトコッカス感染症
・強直性脊椎炎 → HLA-B27(+)
・胸腺腫 → 重症筋無力症
・急性好酸球性肺炎、慢性好酸球性肺炎それぞれの臨床像
・ALL+フィラデルフィア染色体(+) → イマチニブ
・ADPKD → 脳動脈瘤の合併
・薬の副作用関係
(抗甲状腺薬や妊婦に禁忌の薬剤など、3-4問は出題された気がする)
・サルコイドーシス、アミロイドーシスも多数出題
ほか、症例問題も多数。
とにかく全分野からまんべんなく出ます。
各分野の基本的な疾患はすべて出ると考えておいてよいです。
■ 私が使用した教材
・イヤーノート内科・外科編
・クエスチョン・バンク医師国家試験問題解説 vol1-vol5
・Q-Assist 内科・外科 ※オススメ
・データ・マニュアル 各論 内科・外科編 ※オススメ
・日本内科学会HPの過去問集
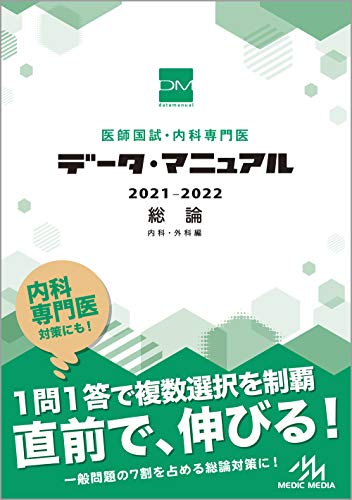
医師国試・内科専門医 データ・マニュアル 2021-2022 総論 内科・外科編
- 発売日: 2020/09/04
- メディア: 単行本
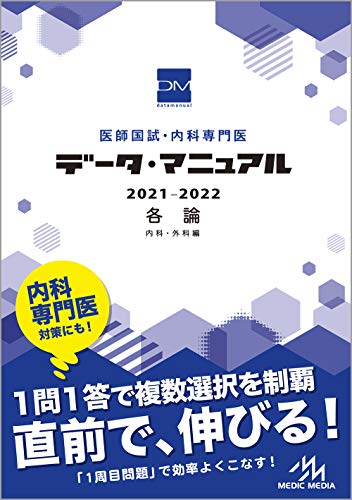
医師国試・内科専門医 データ・マニュアル 2021-2022 各論 内科・外科編
- 発売日: 2020/09/04
- メディア: 単行本
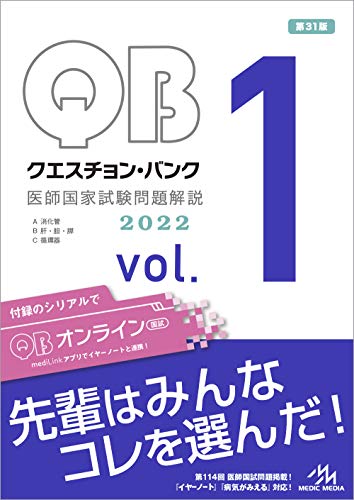
クエスチョン・バンク 医師国家試験問題解説2022 vol.1
- 発売日: 2021/02/16
- メディア: 単行本
まず内科学会HPの「過去問」を購入して解いてみると、5割程度しかわからず、しかも解説もないため焦りました。……かといって、イヤーノートを前から全部読みこむのは非効率的で現実的ではありません。
各予備校から認定内科医のために試験対策用の講座の販売もされています。
しかしどうせやるなら内科全体を復習したいと思い、クエスチョンバンクをvol1-5まで買いました。クエスチョンバンクを購入したのはQB onlineとQ-Assist目当てです。QB vol1-5まで購入すると、QB onlineとQ-Assistという講義を視聴することができるようになります。
データマニュアルの総論も購入しましたが、あんまり使いませんでした。
■ Q-Assist

QB vol1-5まで購入すると「mediLink」からQ-Assistを閲覧可能になります。Q-Assistでは各動画10分程度、各分野10~15時間程度で押さえておくべき疾患の基本的事項・国家試験問題について解説されています(※あとでQ-Assist 個別で購入することもできることを知りました)。
私はこれを仕事の空き時間に少しずつ見て、約3か月かけて内科のほぼすべての動画を見ました。見るだけではなく、データ・マニュアルを併用して要点を書き込みつつ、なるべく記憶が定着するようにしました。Q-Assistの動画は非常に面白く、臨床をある程度経験してから見ると、また違った味わいがあってたいへん勉強になりました。ほか、暇な時間にQB onlineで問題演習を少しやりました。
自分の専門以外の内科疾患を幅広くもう一度復習できたことは、今後の臨床に役立つと思いました。
※Q-Assist 講師の清澤先生が面白くてオススメです。
※ゆっくり見ると、全部見終わるまで3か月程度かかりました。
※上の画像のように各分野の進捗がグラフでわかるようになっているのでやる気が出ます。
■ 試験の手ごたえ
Q-Assistで清澤先生が強く主張していたポイントがそのまま出題される問題が結構あり、そういった問題は一瞬で解くことができました。
普通に国家試験の勉強をすれば、そのまま認定内科医試験対策にもなると思います。
全体的に完璧にできた!という手ごたえはありませんが、合格点には達しているのではないかな??と思っています。
Q-Assistで説明されていない知識が問われた問題もいくつか見られたので、掘り下げたい疾患はイヤーノートで知識を補足しておくといいかもしれません。
■ そのほか
60分と40分の休憩時間はわりとヒマなので、荷物に余裕があればイヤーノートなどを持って行って読むと良いヒマつぶしになります。
■ 試験の結果(2019年9月15日:追記)
合格しました。
なんとか全分野で平均値は上回ることができましたが、苦手分野の内分泌、呼吸器、膠原病はやっぱり低くなってしまいました。
今後も継続してちゃんと勉強したいと思います。
ほぼまっさらの状態から約3か月の勉強でこのくらいなので、普段から勉強している人やもっと時間を作ることができる人は、もっといけると思います。
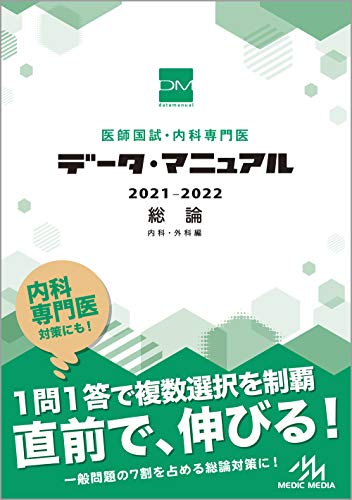
医師国試・内科専門医 データ・マニュアル 2021-2022 総論 内科・外科編
- 発売日: 2020/09/04
- メディア: 単行本
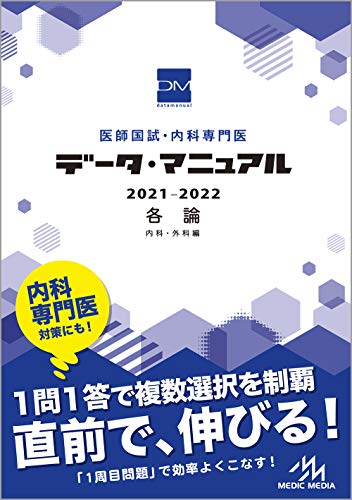
医師国試・内科専門医 データ・マニュアル 2021-2022 各論 内科・外科編
- 発売日: 2020/09/04
- メディア: 単行本
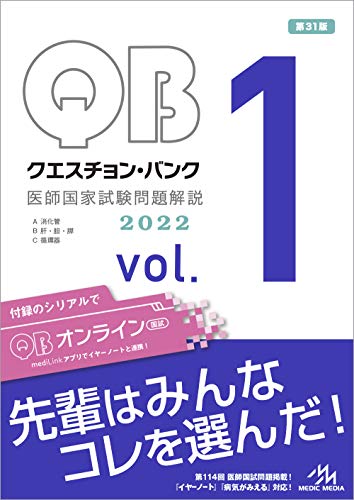
クエスチョン・バンク 医師国家試験問題解説2022 vol.1
- 発売日: 2021/02/16
- メディア: 単行本
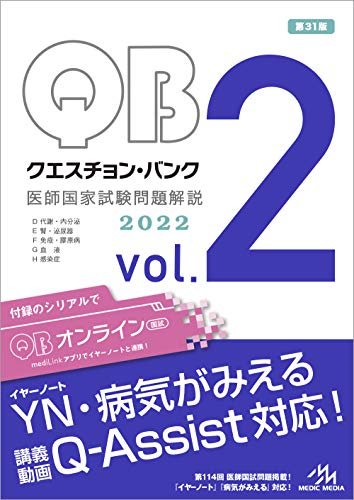
クエスチョン・バンク 医師国家試験問題解説2022 vol.2
- 発売日: 2021/02/18
- メディア: 単行本
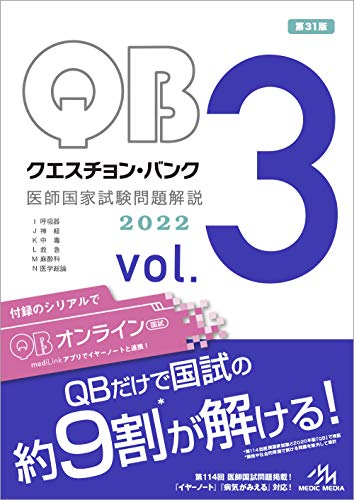
クエスチョン・バンク 医師国家試験問題解説2022 vol.3
- 発売日: 2021/03/02
- メディア: 単行本
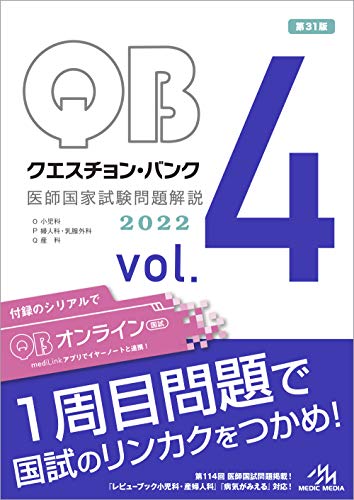
クエスチョン・バンク 医師国家試験問題解説2022 vol.4
- 発売日: 2021/03/03
- メディア: 単行本
【認定内科医試験】日本内科学会 認定内科医試験 過去問題集(第1集)の解答・解説【非公式】
はじめに
第1集には正解選択肢だけが記載されており、解説はありません。
非公式ではありますが、私なりに調べて解説を記載してみたいと思います。
※間違いもあるかもしれませんが、ご容赦ください。
目次
消化管
問題1:進行食道癌の症例。
〇 (a) 食道癌の危険因子は、加齢、喫煙、アルコール、熱い食事の嗜好、肥満など。
× (b)
× (c) 活動性の出血はなく、止血術の適応ではない。
× (d) 進行食道癌にPPIは有効ではない。
× (e) 内視鏡所見上、進行癌のためESDの適応とはならない。
問題2:胃潰瘍の原因について。
〇 (a) 抗コリン薬は原因とはならない。
× (b) H.pyloriは胃潰瘍の二大原因のひとつ。
× (c)
× (d) NSAIDsは胃潰瘍の二大原因のひとつ。
× (e) ガストリン過剰分泌のため胃酸過多となる。
胃潰瘍は、H.pyloriとNSAIDsが二大原因。
攻撃因子を増強させるもの:NSAIDs、インスリン、ヒスタミン、Zollinger-Ellison症候群、副甲状腺機能亢進症など。
防御因子を減弱させるもの:ストレス、慢性肺気腫、肝硬変、関節リウマチ、低栄養、腎不全、糖尿病、NSAIDs、ビスホスホネート製剤など。
問題3:逆流性食道炎の治療薬について。
× (a)
〇 (b) カルシウム拮抗薬はLES圧を低下させるためGERDは増悪する。ほか、硝酸薬もLES圧を低下させる。
× (c)
× (d)
× (e)
内視鏡画像はびらん性GERD(逆流性食道炎)。治療には、①生活指導(禁煙・肥満の是正・就寝時上半身挙上・食直後の前屈位の回避・就寝前の食事・アルコール・高脂肪食・過食の回避など)、②薬物療法(PPI、P-CABなど)、③外科的治療(噴門部形成術:Nissen法、Toupet法)。
問題4:萎縮性胃炎について。
× (a) PFD試験は膵外分泌機能検査。慢性膵炎や膵癌で低下する。
× (b) 食道内圧試験はアカラシアなど、食道運動機能の低下する疾患を評価する。
〇 (c) H.pyloriの感染の有無を評価する。
× (d) pHモニタリングでは胃酸の食道内への逆流の有無や頻度・時間を評価する。
× (e) ツベルクリン反応は結核菌や非結核性抗酸菌症で陽性となる。
× (f) リンパ球刺激試験(DLST)は薬剤アレルギーのうちⅣ型アレルギーをみる。
× (g) α1アンチトリプシン法は蛋白漏出性胃腸症の検査。腸粘膜からの蛋白漏出の程度をみる。
× (h) 抗ミトコンドリア抗体はPBCで陽性となる。
問題5:小腸から分泌されるホルモン。
× (a) レニンは腎臓の輸入細動脈の壁にある傍糸球体細胞から分泌される。
〇 (b) セクレチンは小腸粘膜で合成される。膵臓からの重炭酸塩の外分泌を亢進させる消化管ホルモン。
× (c) ガストリンは胃の幽門前庭部に存在するG細胞から分泌される。
× (d) グルカゴンは膵ランゲルハンス島のA細胞(α細胞)で合成、分泌される。
× (e) カルシトニンは甲状腺の傍濾胞細胞から分泌される。
問題6:NSAIDsによる小腸潰瘍(NSAIDs起因性小腸傷害)。
× (a)
〇 (b) NSAIDsによる消化管障害はシクロオキシゲナーゼ(cyclooxygenase: COX)の活性阻害によって発生する。治療の基本は原因薬剤の中止。
× (c)
× (d)
× (e)
問題7:消化管の蠕動促進作用のある薬剤。
× (a) 蠕動抑制。
× (b) グルカゴンは貯蔵燃料を動員する異化ホルモン。肝での糖新生を促進する。
〇 (c) 蠕動促進。
× (d) ポリカルボフィルは体内非吸収性の過敏性腸症候群の治療薬。
× (e) 蠕動抑制。
問題8:S状結腸軸捻転症。腹膜刺激症状なし。
× (a) 捻転解除に成功しても再発が多い。
× (b) 高齢男性、老人ホーム、精神科病院などに入居している患者に多いとされる。
〇 (c) S状結腸軸捻転症に対しては、腸管壊死がなければ内視鏡的整復が基本。
× (d)
× (e)
問題9:過敏性腸症候群の診断基準。
× (a) 便潜血は陽性にならない。
× (b) 発熱や関節痛は伴わない。倦怠感、不安、頻尿、動悸などの症状を伴うことはある。
× (c) 若年、女性に多いとされる。
× (d) 腸管に器質的病変はみられない。
〇 (e) ROMEⅣ基準では、①排便によって症状が軽快する、②発症時に排便回数の変化がある、③発症時に便形状の変化がある、が診断基準としてある。
肝臓
問題10:「アルコール性肝硬変」で低値を示す血液検査項目。
× (a) γ-GTPは高値となる。
× (b) AST/ALT比は高値となる。
× (c) γ-グロブリンは高値となる(血清蛋白低下の代償などが原因として考えられている)。
〇 (d)
〇 (e)
問題11:経口感染する肝炎ウイルス。
〇 (a) A型肝炎ウイルスは経口感染。
× (b) B型肝炎ウイルスは非経口感染(垂直感染、水平感染(性交渉・針刺し・輸血など))。
× (c) C型肝炎ウイルスは非経口感染(血液や体液)。
× (d) D型肝炎ウイルスは非経口感染(血液や体液)。
〇 (e) E型肝炎ウイルスは経口感染。
問題12:門脈圧亢進症の症状。
× (a) 奇脈:吸気時の収縮期血圧低下が 10 mmHg 以上となり,小脈となる現象。心タンポナーデ、緊張性気胸、収縮性心筋炎、左室肥大、心不全などでみられる。
× (b) 手掌紅斑:肝障害によって血中のエストロゲンが増加した結果、毛細血管が拡張して起こる。
× (c) 希発月経:月経周期が延長し、39日以上3カ月以内で起こる月経。
× (d) 下肢静脈瘤:生活習慣や加齢など、逆流防止弁の機能障害。
× (e) 女性化乳房:アンドロゲン作用低下または エストロゲン作用上昇によって起こる。
× (f) 頸静脈怒張:右心不全の徴候。
× (g) クモ状血管腫:妊娠中のエストロゲン上昇や肝硬変時のエストロゲン不活性化減少などによる。
〇 (h) 腹壁静脈怒張:門脈圧亢進の結果、側副血行路(臍の周りの皮下静脈)が発達する。
全182問。
少しずつ書き足していきたいと思います。
【書評】これだけは読んでおきたい! 消化器内視鏡医のための重要論文200篇 <消化管腫瘍編>【感想】

消化器内視鏡医にとって読むべき重要な論文200篇が、「頭頸部」(5篇)、「食道」(30篇)、「胃」(60篇)、「十二指腸」(5篇)、「小腸」(15篇)、「大腸」(85篇)の6カテゴリー別に収載されています。いずれも1論文1ページの読み切りとなっています。各論文は、その論文のポイントとなる点を簡潔にまとめた「概説」と、その論文の重要性やその論文がもたらした影響・関連する背景などを各執筆者の視点から解説した「解説」で構成されています。
内容紹介より引用:https://cbr-pub.com/book/061.html
オススメ度 ★★★★★
(消化器内科、内視鏡医におすすめ)
内容
静岡がんセンターや国立がん研究センターが共同で作成された本です。食道・胃・大腸のカテゴリ別に200本の消化器内視鏡検査・治療に関する論文が幅広く紹介されています。1ページに1論文が紹介されていて、英文タイトル・研究デザイン・概要(アブストラクト)・解説・結論のシンプルな構成です。
例えば、「胃腫瘍に対するESD後の二次内視鏡検査は推奨されるか?」という疑問については、2015年の論文や2016年の多施設共同研究による論文を基に詳細な解説があり、最後に「ESD術後の確認内視鏡検査を行うことは推奨されない」と説明されています。2018年現在としては常識のように考えられていることの変遷・経緯がはっきりとしたエビデンスとして理解できます。
本書の特徴
1ページ1論文のシンプルな構成で、サクサクと読むことができます。解説が丁寧でわかりやすいので疑問を持つことなく読み通せます。今現在、当然のように考えられていることが、どういった研究を基礎としてできあがってきているのか理解できます。
おわりに
誰でも知っているレベルで有名な論文の紹介もあれば、初めて目にするような論文も多数紹介されていて非常に勉強になりました。消化器内視鏡検査に携わる人間であれば「必読」と言えるレベルの本だと考えます。是非お勧めです。

これだけは読んでおきたい! 消化器内視鏡医のための重要論文200篇 <消化管腫瘍編>
- 作者: 松田尚久
- 出版社/メーカー: シービーアール
- 発売日: 2018/07/10
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

消化器内視鏡第29巻3号増大号 消化器内視鏡の基礎知識と基本テクニック
- 作者: 消化器内視鏡編集委員会
- 出版社/メーカー: 東京医学社
- 発売日: 2017/03/27
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る

消化器内視鏡 Vol.30 No.6(201 どうマネージする?大腸憩室出血・憩室炎
- 作者: 消化器内視鏡編集委員会
- 出版社/メーカー: 東京医学社
- 発売日: 2018/07/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 消化器内視鏡編集委員会
- 出版社/メーカー: 東京医学社
- 発売日: 2017/10/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 出版社/メーカー: 医学書院
- 発売日: 2018/04/16
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る
【書評】早期胃癌2018(胃と腸 2018年 5月号増刊号)【感想】

いきなり他誌の話で恐縮だが,日本胃癌学会の機関誌である「Gastric Cancer」のインパクトファクター(2016/2017)がついに5.454と5点台を超えた.日本発の癌関連英文誌が5点を超える時代が来るとは夢想だにしなかったが,この出来事は,わが国の胃癌研究がこれまで世界をリードし続けてきた証しとも言えよう.長らく診療に携わってきた者の一人として同慶の至りであるが,本誌の序に代えて,ここに至る道程を少し振り返ってみたい.
序説より引用:http://medicalfinder.jp/doi/abs/10.11477/mf.1403201346
オススメ度 ★★★★
(消化器内科、内視鏡医におすすめ)
内容
2018年時点での早期胃癌についての知見をまとめた一冊です。
具体的には早期胃癌の疫学、病理、検査、診断の基本、H.pylori感染・未感染の胃癌とH.pylori除菌後胃癌、早期胃癌の治療・予後、特殊な組織型を呈する早期胃癌(Epstein-Barr virus関連胃癌、カルチノイド・内分泌細胞癌、肝様腺癌、胎児消化管類似癌、胃底腺型腺癌)、遺伝子検査の現状と未来……など。
本書の特徴
早期胃癌の疫学から基本的な内視鏡観察の方法(見逃しやすい部位はどこか?などの基本)、画像強調併用拡大観察(VS classification system)、胃癌治療ガイドライン第5版等の最新のガイドラインの変更点、外科的治療、特殊な胃癌まですべてがこの一冊にまとまっています。
おわりに
「早期胃癌2009」から9年が経ち、本書「早期胃癌2018」が発売されました。本書を読むと、胃癌診療が物凄いスピードで進化していることがよくわかります。今の時代の内視鏡医に必要な知識が網羅されているので、よくまとまっていてすでに知っている知識であっても復習できますし、内視鏡医には必読の一冊だと思います。

- 出版社/メーカー: 医学書院
- 発売日: 2018/04/16
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 日本胃癌学会
- 出版社/メーカー: 金原出版
- 発売日: 2018/02/02
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 日本胃癌学会
- 出版社/メーカー: 金原出版
- 発売日: 2017/10/27
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
再開します。
仕事が忙しく、しばらく更新できませんでしたが、また再開しようと思います。
この2年間で新版が出た本が多いのですが、必ず新しく買いなおして読みます。
情報が古くなっているので、サイトの更新・手直しも随時行っていきます。
【書評】 脳卒中治療ガイドライン2015 【感想】

6年ぶりの改訂となる本書は、従来からの項目については2009年版(~2007年4月)以降の2007年5月から2013年12月までの文献を、新規・変更項目については1992年以降(初版同様)の文献を検索し、さらに2014年1月以降の文献からも、委員会として妥当と判断した重要文献はハンドサーチ文献として採用した。その結果、2009年版で検索した1万件を遥かに凌ぐ、2万3,000件以上の文献から、本委員会のエビデンスレベル分類に従って採択し、推奨グレードを評価した。
紹介文より引用:http://www.kk-kyowa.co.jp/stroke/index.html
オススメ度 ★★
(専門知識を学びたい人におすすめ)
内容
脳卒中関連5学会が総力を挙げて作成した「脳卒中治療ガイドライン2015」は、2004年・2009年に発売されていたものの全面改定版です。
内容は「脳卒中一般(超急性期管理、合併症対策など)」、「脳梗塞・TIA」、「脳出血」、「くも膜下出血」、「無症候性脳血管障害」、「その他の脳血管障害」、「リハビリテーション」に大分類されています。
たとえば、高血圧患者では脳卒中予防のために血圧140/90mmHg未満が強く勧められる(グレードA)、蛋白尿や糖尿病合併例では130/80mmHg未満、後期高齢者では150/90mmHg未満を目標とすることを考慮してもいい(グレードC1)、2型糖尿病患者ではスタチン投与が強く勧められる(グレードA)、喫煙は脳梗塞・くも膜下出血の危険因子であり禁煙が強く勧められる(グレードA)などなど……。
本書の特徴
超急性期の管理からリハビリテーションまで膨大なエビデンスを整理・網羅した分厚い一冊です。病態によって推奨度が明瞭に示されているので非常に読みやすい構成となっています。
おわりに
ちいさな病院では常勤の脳神経外科や神経内科がいないことがほとんどです。
さらに、夜間救急では専門外であろうと一人で脳卒中に対応しなければならないことが多々あります。そういう時にこの一冊があれば役に立つのかなと思って購入しました。実際、知っている内容も多かったのですが、厚いわりには読みやすく具体的な内容が多くて面白く読むことができました。
Wikipediaでは脳梗塞などの項目に未だに「脳卒中治療ガイドライン2009」の内容が引用されています。医療関係者はインターネット上の情報だけではなく、学会やガイドラインなどでアップデートされた情報を自分から得ていく態度であるべきと思います。

- 作者: 日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会
- 出版社/メーカー: 協和企画
- 発売日: 2017/11/01
- メディア: 大型本
- この商品を含むブログを見る

レジデントノート 2017年12月 Vol.19 No.13 一歩踏み出す脳卒中診療〜患者さんの生命予後・機能予後をよくするための素早い診断・再発予防・病棟管理
- 作者: 立石洋平
- 出版社/メーカー: 羊土社
- 発売日: 2017/11/15
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 道免和久
- 出版社/メーカー: 医学書院
- 発売日: 2013/06/17
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 荒木信夫
- 出版社/メーカー: 医学書院
- 発売日: 2015/03/30
- メディア: 大型本
- この商品を含むブログを見る
【書評】 知らなきゃ危ない! 病棟でよくつかわれる「くすり」 エキスパートナース 2016年11月号増刊 【感想】
![全ナース必携!知らなきゃ危ない!病棟でよくつかわれる「くすり」 2016年 11 月号 [雑誌]: エキスパートナース 増刊](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51o5XIDDr2L._SX400_.jpg)
オススメ度 ★★★★
(病棟看護師、初期研修医におすすめ)
内容
タイトル通りの内容で、病棟でよく使われている降圧薬、抗不整脈薬、利尿薬、抗血小板薬・抗凝固薬、下剤、解熱鎮痛薬、オピオイド鎮痛薬、睡眠薬・抗不安薬、不穏に対する向精神薬、抗てんかん薬、血糖降下薬、インスリン製剤、抗菌薬について、薬の作用機序、薬が使われる疾患の基本知識、観察・ケアのポイントが図表を用いて解説されています。
たとえば、下剤のページでは、便秘の分類を図解してから下剤の作用機序、大腸のどこに効くのかが解説される構成になっています。観察・ケアのポイントではブリストル便性状スケール、塩類下剤では高マグネシウム血症の副作用があることやグリセリン浣腸の体位までコンパクトながらも要点を抑えた内容です。
本書の特徴
カラフルでわかりやすい図表が満載です。薬を羅列するだけではなく、全パートにわたって基本的な疾患の解説が最初にあるので、「どういう病態に対してこの薬が使われているのか?」というところが非常に分かりやすくなっています。薬の一覧は2016年11月の最新の時点までカバーしてあり、観察・ケアのポイントも要点をしっかり抑えてあります。
おわりに
目を引くタイトルに惹かれて購入しましたが、「薬がみえる」を病棟看護師向けに特化させて内容を絞り込んだような本でした。病棟看護師に向けて作られている本ですが、この本に書いてある内容を完璧に理解している医師も少ないのではと思います。
本書に出てくる図表はすべてキレイに作られていて内容も十分、大変勉強になりました。全129ページ程度と薄めなので、ササッと読めるのが良かったです。病棟にひとつ置いておくと便利かなと思います。
![全ナース必携!知らなきゃ危ない!病棟でよくつかわれる「くすり」 2016年 11 月号 [雑誌]: エキスパートナース 増刊 全ナース必携!知らなきゃ危ない!病棟でよくつかわれる「くすり」 2016年 11 月号 [雑誌]: エキスパートナース 増刊](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51o5XIDDr2L._SL160_.jpg)
全ナース必携!知らなきゃ危ない!病棟でよくつかわれる「くすり」 2016年 11 月号 [雑誌]: エキスパートナース 増刊
- 出版社/メーカー: 照林社
- 発売日: 2016/10/20
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る
![知らなきゃ危ない!病棟でよく使われる「くすり」 Part.2 2017年 08 月号 [雑誌]: エキスパートナース 増刊 知らなきゃ危ない!病棟でよく使われる「くすり」 Part.2 2017年 08 月号 [雑誌]: エキスパートナース 増刊](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51D2DL5AmDL._SL160_.jpg)
知らなきゃ危ない!病棟でよく使われる「くすり」 Part.2 2017年 08 月号 [雑誌]: エキスパートナース 増刊
- 出版社/メーカー: 照林社
- 発売日: 2017/07/20
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 愛媛大学医学部附属病院薬剤部,荒木博陽
- 出版社/メーカー: 照林社
- 発売日: 2018/04/27
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 医療情報科学研究所
- 出版社/メーカー: メディックメディア
- 発売日: 2014/10/31
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 医療情報科学研究所
- 出版社/メーカー: メディックメディア
- 発売日: 2015/07/08
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 医療情報科学研究所
- 出版社/メーカー: メディックメディア
- 発売日: 2016/11/30
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
【書評】 胃と腸 2016年1月号 慢性胃炎を見直す 【感想】

オススメ度 ★★
(専門知識を学びたい人におすすめ)
内容
「慢性胃炎」の歴史、病理診断、内視鏡診断(拡大内視鏡診断)、臨床診断(血清診断)、A型胃炎の診断、残胃炎などの知見をまとめた一冊です。
胃炎の歴史は古く、多様な分類が呈示されていますが、日本では2014年の第85回日本消化器内視鏡学会総会から「胃炎の京都分類」が新たな胃炎分類として提案されるようになりました。
本書ではこれまでの胃炎分類の歴史、「Updated Sydney System」と「胃炎の京都分類」を中心に慢性胃炎の組織学的病理学的な違いについて、専門の筆者ごとに記事をわけて、大変わかりやすく記載されています。
本書の特徴
きれいな内視鏡写真が豊富でヘリコバクターピロリ菌除菌前・除菌後の違いがわかりやすくなっています。胃炎の京都分類についてはわかりやすくテーブル表記、画像も大きく掲載してあります。
おわりに
本書を読んでみて今一度勉強になりました。日本で上部消化管内視鏡検査に携わる人は、これからは完璧とは言わなくても京都分類の方法を知っておく必要があると思います。
胃と腸では今後「胃炎のすべて」という企画を増刊で考えている(?)らしく期待しています。

- 出版社/メーカー: 医学書院
- 発売日: 2015/12/28
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 春間賢,加藤元嗣,井上和彦,村上和成,鎌田智有
- 出版社/メーカー: 日本メディカルセンター
- 発売日: 2014/09/24
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

H.pylori感染の診断と治療のガイドライン 2016改訂版
- 作者: 日本ヘリコバクター学会ガイドライン作成委員会
- 出版社/メーカー: 先端医学社
- 発売日: 2016/08/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る